この記事では
・理想の身体を作りたい
・タンパク質についてあまり知識がない
という人のために
わかりやすくタンパク質について現役の理学療法士が解説していきます。
ダイエットやトレーニング初心者の人はもちろんですが、
トレーニングや栄養に関する研究論文も解説していきますので、
トレーニング中級者以上の人でも楽しめる内容となっています。
ぜひ最後までご覧ください。
タンパク質とは何か?

タンパク質は、体を作る栄養素です。
主に、筋肉や内臓、皮膚、血液、爪、髪といったものを作るのに重要な働きをします。
タンパク質の不足は、体を作れないことに加え、
免疫力低下、筋力低下といった悪影響も生じます。
タンパク質を正しく取ることは、筋肉の成長、体調維持のために、とても重要です!
覚えておきたい三大栄養素
- 炭水化物(糖質)
- 脂質
- タンパク質
この三大栄養素が体を動かすエネルギーとなります。
主に炭水化物(糖質)と脂質が体を動かすエネルギーになります。
タンパク質は体作りに使われ、使われなかった分がエネルギーになります。
体作りには必須栄養素なので覚えておきましょう!
タンパク質と筋肉の関係
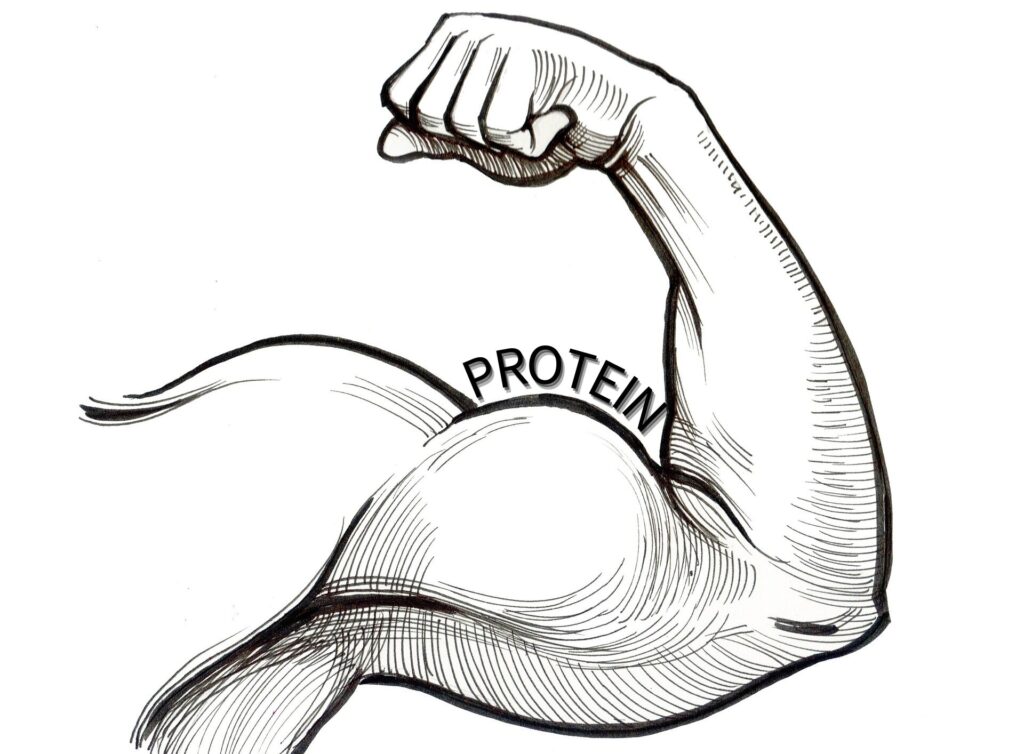
筋肉が体重に占める割合をご存知ですか?
なんと体重の約40%が筋肉と言われています!
体重60kgの人だと、約24kgが筋肉ということになります。
筋肉は、その70〜80%が水分であり、残りのほとんどがタンパク質になります。
筋肉はカラダにおけるタンパク質の貯蔵庫の役割を果たしています。
そしてトレーニングは、筋タンパク質合成を強く促進する刺激であり、タンパク質の摂取とトレーニングをうまく組み合わせていくことが、効率よく筋肉を作るコツになります!
タンパク質はどのくらい必要?

では、1日にどのくらいのタンパク質が必要になるのか?
厚生労働省が発表した「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、
男女ともに「タンパク質維持必要量(平均値)=0.66g/kg体重/日」とされています。
細かな計算は省きますが、日本の成人男性で60〜65g、成人女性で50gのタンパク質が1日に必要と推奨される量となります。
一般的に、激しい筋トレをする場合は、通常の1.5〜2倍のタンパク質を摂取することが勧められています。
タンパク質の過剰摂取は体に悪影響がある?!
「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、
タンパク質の過剰摂取に関する内容に以下のようなことが書かれています。
「たんぱく質摂取量と腎疾患へのリスクに関する研究をまとめた2023年のアンブレラレビューでは、観察期間が短いなどの課題が残されているものの、高たんぱく質摂取により腎疾患の発症を高める、という結論には至らなかった。したがって、現時点ではたんぱく質の耐容上限量は設定しないこととした。」
よって時折騒がれる、「プロテインの飲み過ぎは危険!」と言った情報に、
現時点での科学的根拠はないと言えます。
ただし、上記の文章の後には、
「たんぱく質の推奨量以上の摂取により、他の健康指標に対し有益な影響を得られるという根拠が乏しいことが報告されていることから、上限のないたんぱく質の摂取が健康増進に有益な効果をもたらすわけではない点には注意が必要である。」
とも書かれていました。
「タンパク質ばかり摂取しても意味ないよ」ということですね。
タンパク質はいつ摂取すればいい?
結論から述べますと、『24時間〜48時間以内なら、いつでもいい!』
トレーニング中級者になると、
『タンパク質は運動直後に摂取!』
『運動後40分くらいがタンパク質摂取のゴールデンタイムだー!!』
という情報をよく耳にすると思います。
トレーニング直後の摂取には効果がある
2001年、Esmarckさんたちの研究でこのような結果がわかりました。
レジスタンストレーニング(筋トレ)直後にタンパク質を摂取した人たちと、筋トレした2時間後にタンパク質を摂取した人たちでは、運動直後に摂取した人たちで有意にタンパク質合成率が高かった。
参考文献:Timing of postexercise protein intake is important for muscle hypertrophy with resistance training in elderly humans.
「やっぱり直後がいいんじゃん!!」と聞こえてきそうですが、
研究は結果の数値データだけでなく、その被験者って誰なの?
ってところにも目を向けることがとても大切です。
Esmarckさんらの研究で対象となったのは、70〜80歳の男性13人です。
なお、この13人は、過去5年間筋力トレーニングなどは行っていなかった方々を対象としています。
これを聞くと、「ん?筋トレをしたことのない、たった13人の高齢男性のデータって信用してもいいのかな?」って疑問に感じませんか?
ここがポイントです。
このデータで「筋トレ直後にプロテインを飲みましょう!」というには少し強引なんです。
この13人のデータがたまたまなのかもしれないという可能性は捨てきれません。
じゃあ、もっと大人数での研究結果はないのか?と思い検索すると、ちゃんとありました。
トレーニング直後の摂取じゃなくても効果はある
2020年、Wirthさんらが発表した研究結果は以下のようなものでした。
男女合わせて2907人を対象とし、18〜55歳と、55歳以上の高齢者で比較しています。
この結果、タンパク質の摂取タイミングに関係なく、筋肉量増加に効果があった。
参考文献:The Role of Protein Intake and its Timing on Body Composition and Muscle Function in Healthy Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.
なお、この研究は「システマティックレビュー」と呼ばれ、たくさんの研究論文を調査する研究手法で、信頼性が高い手法といわれています。
結論:タンパク質摂取のタイミングはいつでもいい
13人の高齢男性のデータと、2907人の老若男女のデータ、どちらを信頼するなんてことは言わずもがなですよね。
このことから、もう一度言わせてもらいますが、
摂取するタイミングは? 『いつでもいい』 となるわけです。
ただし、いつでもいいと言っても、限度というものがあります。
Phillipsさんらの研究によると、
筋トレ後のタンパク質合成速度が増加しているのは、運動後24〜48時間までの間である。
参考文献:Mixed muscle protein synthesis and breakdown after resistance exercise in humans.
よって、筋トレをしたら、以後48時間は筋肉が作られやすい体になっていますので、その間、しっかりとタンパク質を多く含む食事を心がけましょう!
ジムでの筋トレが終わり、急いでタンパク質を摂取しないとー!って躍起になるよりも、ジムでは、「筋肉に刺激を入れるにはどうしたらいいのか」「どのくらいの量をするべきか」などに、意識を向けていきましょう。
タンパク質が多く含まれる食材は何?

タンパク質を多く含む食材(料理)で、身近で手に入れやすいものを抜粋しました。
高タンパク質料理を作る際の参考になれば幸いです。
文部科学省の食品成分データベースをもとにした、食材100gあたりのタンパク質含有量は以下の通りになります。
肉類
- ビーフジャーキー 54.8g
- 豚肉 39.3g
- 鶏胸肉 38.8g
- ササミ 36.1g
- 牛肉 31.0g
魚介類
- かつお節 77.1g
- するめ 69.2g
- 帆立貝 65.7g
- イワシ丸干し 32.8g
- 紅鮭 28.5g
卵類
- 目玉焼き 14.8g
- ゆで卵 12.5g
- ポーチドエッグ 12.3g
- 生卵 12.2g
- 厚焼きたまご 10.5g
豆類(大豆製品)
- きな粉 35.5g
- 油揚げ 18.6g
- 納豆 16.5g
- 厚揚げ 10.7g
- 豆腐 6.6g
タンパク質はどのように摂取すればいい?

普通の生活をしていれば、食事は1日3回であり、その3回の食事で必要量のタンパク質を摂取できないことも多いと思います。
そんな時に、プロテインドリンクを飲む方も多いのではないかと思います。
私自身も、食事でもたんぱく質摂取を心がけていますが、主に食事を作ってくれる妻に無理をいうわけにもいきませんので、プロテインドリンクを活用しています。
私は、色々試してきましたが、高品質、低価格のMYPROTEINを愛用しています。
MYPROTEINは、2004年マンチェスターで創設。70か国以上で販売を行っているスポーツ栄養ブランド大手になります。
海外製品で、以前は注文してから手元に届くまで、何週間もかかりましたが、今では数日間で届くようになったため、とても利用しやすくなっています。
まだ試したことのない方は是非一度試してみてください。
ちなみに、私の一押しフレーバーは、「ナチュラルチョコレート」です。
(2026/02/04 05:50:25時点 楽天市場調べ-詳細)
まとめ
筋トレで理想の体を作るには、トレーニングだけでなく、タンパク質などの栄養をしっかりと摂取することが大切です。
成人男性で60〜65g、成人女性で50gのタンパク質が1日に必要と推奨される量となり、筋トレをしているヒトに関しては、1.5〜2倍の量が勧められています。
摂取するタイミングは、筋トレ直後にこだわる必要はなく、筋トレ後24〜48時間以内を目安に摂取しましょう。
それでは、栄養摂取もトレーニングの一環であると捉え、
効率よくトレーニングを進め、理想の体を手に入れましょう!








